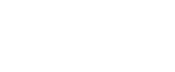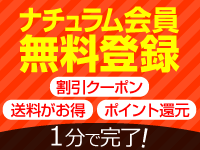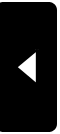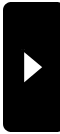2016年06月06日
まり動かないの

「ねえ、モトさん知ってる? 三毛猫って、ほとんどがメスなんだって。何でか分かんないんだけど。だから、モトさんのミケは、すっごく珍しいんだよ。オスだもん。神様のうっかりミスかもね」
由希はモトさんの猫の頭を撫でながら、楽しそうに言った。
もう一時間も由希は、この公園の隅に敷かれたダンボールの上に寝そべったまま、モトさんを相手に他愛もない話を続けていた。
モトさんは、いつものように拾った週刊誌を枕にして寝転がったまま、ニコニコしながら由希の話を聞いている。
皺のたくさん刻まれたその笑顔を見ているだけで、由希は心の中がほわりと温かくなってくるのだ。
9月半ばの夕暮れの風は幾分ヒンヤリとして心地よく、夏には感じられなかった乾いた土埃の匂いがした。
緑豊かで広大なこの泉ヶ丘緑地公園は、私鉄駅のすぐ近くにあった。
公園東側の森林部分では、住居を持たない人々が、ダンボールや廃材で器用にブースを作り、寝起きしている。
公園を通りがかる人々も特に干渉はせず、見えないものとして彼らを容認している。
そんな、奇妙な場所だった。
何が切っ掛けだったのかは忘れてしまった。
気が付いたら由希はこの場所に毎日通うようになっていて、そして数人のホームレスと親しくなっていた。
あれは高校に行かなくなった、昨年の今頃だろうか。
自分の中で、何かが壊れそうになっていた時だった、と。時たまそんなふうにぼんやり思い返す。
由希は本来なら高校2年生のはずだった。
「ミケ、この頃毛が抜けるね。シロウさんのチャトラは、しっぽが禿げてたよ」
あまりにも返事を返してくれないので、由希はミケを抱いたままモトさんを覗き込んだ。
「具合悪いの?」
モトさんは、そんな由希の仕草が可笑しかったのか、喉のおくでクックと笑いながら、左手を伸ばして由希を抱き寄せた。
モトさんの右手は、昔やった病気のせいで、あだという。だからいつも、左手だけで由希を撫でてくる。
由希は、その左手が好きだった。
抱えていたミケの体を離し、コロリとモトさんの横に転がると、もう一度撫でられた。
気持ちよくて、心の奥が痺れてゆく。
土の匂いと、太陽の匂いがした。
このままこうやって転がって繋がって、モトさんの体の一部になれたらどんなに幸せだろう。
動かない右手と、少し麻痺した舌の代わりになれたら、どんなに幸せだろう。
そうやって、溶けて無くなってしまえたら???。
由希はそんなことを思いながら、束の間目を閉じた。
「ありゃ。またモトやんのところにちっこい猫が入り込んどる。ミケがヤキモチ妬いて、俺んとこ来るはずやわ」
突然快活な声が降ってきて由希が目を開けると、両脇に二匹の猫を抱えたシロウが上から覗き込んでいた。
右側にモトさんのミケ。
Posted by zuivindd at 12:18│Comments(0)